はじめに
今回は環境デュー・デリジェンス(以下「環境DD」といいます。)について説明していきます。
地球規模の環境危機が深刻化する中で、企業には単なる法令遵守を超えた責任が求められるようになっています。
EUの企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(以下「CSDDD」といいます。)の発効や、CSRDによるサステナビリティ情報開示の義務化を背景に、企業は自社およびバリューチェーン全体の環境リスクに向き合い、実効的な環境DDを実施することが不可欠となっています。
このような状況の中で、2025年4月28日、環境省が「日本企業による 環境デュー・ディリジェンス 対応促進に向けた懇談会 議論のまとめ」を公表しました。
今回は、この内容を踏まえて環境DDについて考えてみます。
環境DDとは何か
そもそも環境DDとは何か、というところから説明します。
環境DDとは、企業が自らの事業活動やバリューチェーン全体において、環境に対する実際または潜在的な負の影響を特定・評価し、それらに対して予防・是正措置を講じる一連の継続的なプロセスを指します。
国際的には、OECDガイドラインや国連ビジネスと人権に関する指導原則などを踏まえて整備されており、企業のサステナビリティ責任の一環として位置づけられています。
特に環境DDは、以下のようなステップで構成されます。
- リスクの特定:自社および取引先等の活動によって環境に与えうる影響を洗い出す
- リスクの評価:その深刻性や発生可能性を分析する
- 予防および是正措置:影響を防止・軽減・修復するための行動をとる
- モニタリングとフォローアップ:対応措置の有効性を継続的に検証する
このような環境DDの導入は、EUにおけるCSDDDや、企業サステナビリティ報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive、以下「CSRD」といいます。)などの規制において企業に法的義務として課される方向にあり、日本企業にとっても急務の課題となっています。
環境DDにおけるステークホルダーとの「意味のある対話」:リスク把握と対応の出発点
環境への負の影響を「深く」理解すること
企業活動が直接・間接的に環境に与える影響は、企業内部では見えづらいと考えられます。
そのため、バリューチェーンに関わる従業員、地域住民、労働組合、NGOといった多様なステークホルダーとの双方向の対話、すなわち「意味のある対話」が必要になります。
これにより、企業は影響の全体像を把握し、環境リスクの実態に即した対応が可能になります。
優先順位付けと措置の正当性確保
環境DDは「リスクベースのアプローチ」に立脚しており、影響の深刻度や発生可能性を踏まえて対応の優先順位を定める必要があります。
この過程でもステークホルダーとの対話が重要です。企業独自の判断によるリスク認識に偏らず、外部の視点を取り入れることで、実効性と正当性のある対応が実現できます。
危機的状況を「未然に防ぐ」コミュニケーション基盤
信頼関係を日常的に構築しておくことは、環境リスクが社会問題化し、訴訟や制裁の対象となる前に、対話によって緩和・解決する手段ともなります。
特にEU域内では、CSDDDに基づき企業の民事責任が問われるリスクがあり、事前のエンゲージメントが企業防衛としても機能します。
環境DDの実務:ステークホルダー対話の対象・手段・タイミング
誰と対話すべきか?
最も重要なのは、企業活動によって人権や環境に負の影響を受けるおそれのある人々(ライツホルダー)との対話だと考えます。
ただし、すべての当事者と直接対話することが難しい場合は、地域のNGOや専門家、住民団体を通じた間接的な対話も現実的な手段として有効です。
いつ、どのように対話すべきか?
CSDDDでは、以下の5つのフェーズでの対話が義務付けられています:
| フェーズ | 対話の目的 |
|---|---|
| 1. リスク特定 | 潜在的な負の影響の洗い出し |
| 2. リスク評価 | 重大性・発生可能性の評価 |
| 3. 防止措置の計画 | 優先順位に基づいた対応方針策定 |
| 4. 是正措置の実行 | 対応策の運用・モニタリング |
| 5. 継続的なフォローアップ | 長期的な対話と信頼構築 |
環境デュー・ディリジェンスにおける情報開示の重要性
環境DDは「開示によって完成する」
環境DDにおいて、プロセス全体の開示は単なる報告義務ではなく、DDの一部として不可欠だと考えられます。
企業がどのような影響を特定し、どのような措置を講じたのかを対外的に示すことで、信頼性を確保し、フィードバックを得る機会にもなります。
サステナビリティ情報開示との統合的対応
EUのCSRDにより、サステナビリティ報告(ESRS)においても環境DDに基づく情報開示が求められています。
ダブルマテリアリティ評価(企業の発展や活動、ポジション及び幅広く企業価値へのインパクトと、企業活動により生じる様々な関係者に与える環境・社会インパクト、の二つの側面から重要課題を考える評価方法)とDDを一体として捉え、リスク評価の根拠として環境DDの結果を活用する必要があります。
共創的な関係構築:透明性が信頼と共感を生む
環境リスクが「ない」と主張することよりも、「リスクがあることを前提にどう向き合うか」を示す開示の姿勢の方が重要だと考えられます。
具体的には、以下に事例を挙げますEnelはステークホルダーとの対話回数やリスク特定の手法を、Casinoは対話相手とその結果までを開示しています。
実務に活かせる先行事例
Enel(イタリア)
同社は、ステークホルダーと環境・人権リスクの特定に向けてどのように関与しているかを段階的に整理したうえで公開しています。
特定された優先リスクごとに、どのような対話を、どの頻度で、どのような媒体で行っているかを体系的に開示しており、透明性の高い運用が特徴です。
たとえば、サプライヤーとの環境リスク対話や、地域住民との懇談の実施回数も具体的に記載されています。
また、リスク評価と対話プロセスの整合性を保つ工夫として、内部ガバナンス体制との連携にも言及しています。
Casino Guichard-Perrachon(フランス)
フランスの小売大手Casinoは、特に森林伐採に関するリスク管理で注目されました。
同社は、サプライヤーにおける違法伐採や土地収用といった重大リスクに対して、NGOや現地市民団体との対話を通じて情報収集を行い、その内容をURD(Universal Registration Document)で詳細に開示しています。
さらに、注意喚起されたリスクに基づき、自社のリスクマップを見直し、調達ポリシーの改善に繋げた取り組みも公開されています。
同社は透明性に欠けた企業が提訴された事例を踏まえ、環境NGOとの協働によるモニタリング体制の構築に取り組んでおり、エンゲージメントの深化と情報開示の両立を図っています。
まとめ
環境DDは、書類上のコンプライアンスではなく、企業の在り方そのものを見直すプロセスといえます。
ステークホルダーとの「意味のある」対話と、誠実な情報開示は、リスクの可視化と対応の正当性を支えると同時に、企業価値向上の原動力になるはずです。
特に日本企業にとっては、既存の環境マネジメントシステムや地域住民とのコミュニケーションの蓄積を活かしつつ、今後のグローバル基準に即した対応が求められます。






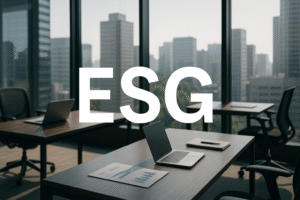


コメント