はじめに
今回は再エネ発電事業者の倒産・清算について説明していきます。
再生可能エネルギーの導入が急拡大する一方で、発電事業者の経営破綻が相次いでいます。帝国データバンクが2025年5月に発表した「『発電所』の倒産・休廃業解散動向(2024年度)」によると、2024年度における発電関連事業者の市場退出件数が過去最多を記録しました。
この現象は単なる業界の一時的な波ではなく、FIT制度の終焉や電力市場の構造的変化、人手不足といった複合的な要因が背景にあります。
本記事では、最新の統計を踏まえ、再エネ事業者を中心とする発電業界の現状と将来を考察します。
帝国データの記事のまとめ
上記調査レポートによれば、2024年度(2024年4月~2025年3月)における「発電所」関連事業者の倒産・休廃業・解散の合計件数は52件であり、これは2014年度の調査開始以来、過去最多であったとのことです。
- 倒産(法的整理):8件(前年同期比33.3%増)
- 休廃業・解散:44件(前年同期比18.9%増)
倒産件数としては大規模ではないものの、「事業継続を断念した事業者」の総数、つまり破産手続等会社の清算に進むようなプロセスを採る会社が増える場合、中長期的にみると再エネ業界の業界構造へ影響を及ぼしかねず、件数としてはこの懸念が生まれる程度の件数になっているように思われます。
特に、設備投資を済ませた後の維持費用が経営を圧迫し、収益改善の見込みが立たないことを理由に自主的に退出を選ぶケースが多数を占めていると思われます。
また、倒産や休廃業に至った事業者の多くは、2012年のFIT制度導入後に参入したり、法人を立ち上げたりした中小規模の太陽光発電事業者です。
これらの企業は、当初、買取価格の高さを前提に事業計画を組んでいたものの、制度変更・価格下落に対応できず、コスト増や設備老朽化といった課題への対応力の差が如実に表れています。
他方、木質バイオマス発電所に関しても、燃料価格の高騰やメンテナンス費用の増大、供給インフラの脆弱性といった問題が顕在化しており、事業継続が難しいと判断する事業者が相次いでいます。
このような市場退出の傾向は、単なる経営判断だけでなく、売電契約の見直しや新電力の相次ぐ撤退といった外部環境の変化とも密接に関係していることが読み取れます。
倒産が増えている背景
発電事業者の倒産・休廃業が増加している背景には、次のような複合的要因があります。
FIT買取価格の引下げと終了
固定価格買取制度(FIT)は、導入当初こそ高値で再エネ電力を買い取ることで発電所の設立を後押ししてきましたが、近年は買取価格の急速な引き下げが進行し、発電事業者にとっては採算の見込みが立たない事態になっているのではないかと思われます。
燃料・資材費の高騰
例えば木質バイオマス発電においては、国内外の木質チップやペレットの価格が高騰し、維持費用が上昇し、採算が悪化していることも理由として挙げられます。
また、太陽光発電所においてもパネルやインバーターの調達コストが上がっており、キャッシュフローを悪化させる要因となっていると考えます。
設備不具合と修繕コストの増加
運転開始から数年が経過した発電設備では、徐々に部品交換や修繕が必要になる箇所が出てくるものと思われます。
こうした部品交換や修繕を怠ると設備トラブルの発生で一部・全部の発電停止が必要となり、これが必然的に売電収入を減らす要因となり得ます。
人手不足
特に地方の発電プロジェクトでは、技術者や保守要員の確保が困難となり得ます。
私の前職でも、地域によってはメガソーラーでは設置が必須となる電気主任技術者の選任に苦労するところがありました。
若手の電気主任技術者が少ないということも聞いており、電気主任技術者全体の高齢化によりますます選任が難しくなる可能性もあります。
今後の動向予測
発電事業者を取り巻く環境は、今後も厳しい状況が続くと見込まれます。
今後予測される主な動向は以下のとおりです。
FIT制度の終了とFIP制度への本格移行
FIT制度は(経済的にはすでに実質終了しているようなものですが)今後段階的に終了し、FIP(Feed-in Premium)制度への移行が進みます。
FIP制度では、再エネ電力が市場価格で取引されることを前提とし、一定のプレミアムを加算する形となるため、電力市場価格の変動リスクを発電事業者が負うことになります。
特に、市場動向の予測や調整力のない中小事業者にとっては、経営の安定性を確保することが困難になるおそれがあります。
再エネ賦課金制度の構造的見直し
再エネ普及に伴う賦課金(電気料金に上乗せされる再エネコスト負担)の上昇が社会的議論を呼んでおり、政府は今後、制度全体の見直しを検討する可能性があります。
FIT価格が変更される、といった事態にまでは及ばないと考えられますが、制度全体の見直しを通じて支援の対象や水準が再調整されると、事業計画の見直しが必要になる発電事業者も増えると考えられます。
まとめ
帝国データの記事が示すように、再エネ発電所の倒産・休廃業は再エネ業界の構造的課題を浮き彫りにしているように思われます。
かつての政策的ブームによって急拡大した再エネ発電市場は、今まさに「選別のフェーズ」に入りつつある、といえます。
事業者にとっては、単に発電するだけでなく、電力市場の動向を踏まえた収益設計、市場価格に連動する制度への対応、そしてメンテナンスや人材確保を含めた長期的な運営計画が求められています。
今後の業界再編のなかで生き残るための鍵は「事業をスケールしつつ持続可能な事業モデルの構築」と言えるかもしれません。






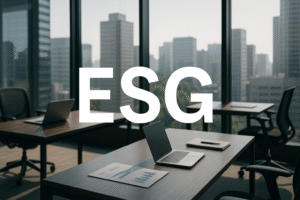


コメント