はじめに
今回は「RE100」について触れてみます。
脱炭素経済への転換が国際的に加速するなかで、企業が再生可能エネルギーを導入する動きが急速に進んでいます。
その象徴的な取り組みが「RE100」への参加です。
RE100は、企業が消費電力の100%を再生可能エネルギーで賄うことを誓約する国際的なイニシアチブであり、日本企業にとってもブランド価値の向上や投資家対応の面で重要な役割を果たしています。
RE100についてなじみがない読者の方もいらっしゃるかもしれませんので、そもそもRE100とは何か、というところから説明していきます。
後で説明しますが、私個人としては、各国の電力政策に影響を与えうる(そしてすでに与えているかもしれない)取組みだと考えています。
RE100とは何か
RE100は、The Climate GroupとCDPが主導する国際的な企業連合で、参加企業は自らの使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替えることを約束することになります。
2024年時点で、世界で400社以上、日本企業では約70社が参加しており、製造業、IT、金融、小売といった多様な業種の企業が参加しています。
RE100の意義は、単なる目標設定にとどまらず、参加企業は、年次報告によって進捗状況を透明に開示する義務を負い、世界の投資家やNGO、市場関係者の注視を受けながら、計画的に再エネ導入を進める必要がある点に特徴があります。
事例紹介:リコーおよびイオンのRE100対応と再エネ導入
日本企業の中でも先駆的な存在がリコー株式会社です。
同社は2023年4月に、日本国内での電力使用の100%を再生可能エネルギー由来に切り替えたと発表しました。
「リコーとSansan、中堅・中小企業における経理業務DX促進に向けた業務提携に合意」
同社はRE100に2017年に参加し、自社拠点での再エネ導入、再エネ証書の活用、さらにはコーポレートPPAの締結など、多様な手法を組み合わせて対応を進めてきたようです。
この取組みにより、グローバルサプライチェーン上のESG要請に応える体制を強化しています。
また、流通大手のイオン株式会社も、2020年時点でRE100に参加し、2040年までに店舗等での使用電力をすべて再生可能エネルギーに転換するという目標を掲げています。
同社は、ショッピングモールの屋根上太陽光や、PPAスキームを活用した外部再エネ電源の調達により、段階的に達成を目指しているようです。
「AEON Report 2024」
RE100参加企業の傾向と拡張的影響
RE100に参加している企業の中には、Google、Apple、Microsoftといった米国のIT大手が名を連ねています。
これらの企業は、大量の電力を消費するデータセンターを世界中に設置しており、その電力の100%を再生可能エネルギーで賄うという姿勢を強く打ち出しています。
この動きが与えた影響は、ホスト国の電力市場の構造そのものにまで及んでいます。
例えばマレーシアでは、電力の小売は国営のTenaga Nasional Berhad(TNB)により独占的に供給されています。
しかし、再エネ導入のニーズが高まる中で、2021年からLarge Scale Solar (LSS)スキームや、自己消費型再エネに加えて、Third Party Accessの議論が始まり、Corporate Renewable Energy Supply Scheme (CRESS)に基づいて、2024年時点ではフィジカルPPA(直接の電力売買契約)も制度上認められるようになっています。
(真偽のほどは分かりませんが、上記のRE100加盟企業からマレーシア政府に対する、フィジカルPPAを認めることを求めるロビー活動があったとも聞いています。)
つまり、RE100企業の進出や投資意欲が、単なる環境配慮にとどまらず、国によっては、そのインフラ制度設計そのものに変革を迫っているともいえます。
日本企業が直面する課題と展望
一方で、日本企業がRE100を目指す際には、電力の供給構造や価格の硬直性、証書の非追加性への懸念など、いくつかの課題があります。
特に、非化石証書などの再エネ証書に依存した取組みは、外部からグリーンウォッシングと批判される可能性もあります。
それでも、RE100参加は、企業の持続可能性戦略の中核を担うものであり、PPAの活用やアグリゲーターとの連携、オンサイト発電設備の導入など、多様な戦略が模索されています。
まとめ
上記のとおり、RE100は単なる認証制度にとどまらず、他国のインフラに影響を及ぼしうる取組みと考えられます。
参加企業に求められるのは、透明性、追加性、実効性の3点を備えた再エネ導入です。
そして、これらの企業行動は、各国における電力制度の改革や地域経済の構造転換をも促進しうることになります。
企業による再エネ選択が、やがて国家のエネルギー政策や国際的な供給網全体に波及することから、RE100という取組みと、その参加企業の活動については注視していく必要がありそうです。






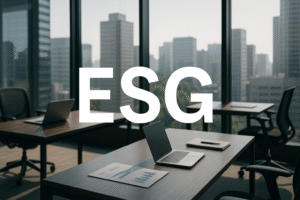


コメント