✅ ざっくり言うと
・非化石証書は、再エネ由来の電気に「環境価値」を与える国の制度。
・FIT/非FITやトラッキングの有無で種類が分かれ、用途や市場での活用が変わる。
・購入方法や他の証書との違いを理解することで、企業の再エネ戦略に直結。
はじめに
今回は非化石証書について説明していきます。
脱炭素社会への移行が叫ばれる中、多くの企業や自治体が再生可能エネルギーの活用を模索しています。
そうした動きの中で注目されてきたのが「非化石証書」です。
名前だけは知っていても実際に詳細を知らない人が多いのが実情なのではないかと思われ、その仕組みや活用方法はまだ十分に周知されているとはいえないのではないかと考えています。
非化石証書は、電力そのものではなく、その電力が非化石エネルギー由来であるという環境価値を証明するもので、国内外の環境対応における一つの選択肢となっています。
以下、非化石証書の仕組みや購入方法、活用のメリットと注意点、そして他の環境価値証書との違いについて説明していきます。
非化石証書とは?
非化石証書とは、非化石電源(再生可能エネルギーや原子力発電など)によって発電された電力が持つ「環境価値」のみを切り離して証書化し、取引できるようにした制度です。
実際に消費者が利用する電力は、発電所から送電網を経由して混ざり合って供給されており、その電力がどのような電源由来かを直接的に把握することはできませんが、環境価値を別に証書として扱うことで、再エネ導入や温室効果ガス排出量の削減努力を可視化・証明する手段として活用されているのが非化石証書、ということになります。
エネ庁の2018年(7年前!)の、非化石証書制度が開始する前の、非化石証書を紹介するウェブサイトがありましたのでご紹介します。
2018年5月から始まる「非化石証書」で、CO2フリーの電気の購入も可能に?
非化石証書の種類
非化石証書には主に3つの種類があります。
以下それぞれ説明していきます。
FIT非化石証書
FITに基づいて発電された電力の環境価値を証書化したものです。
太陽光・風力・中小水力・地熱・バイオマスなどの再エネ電源が対象であり、発電事業者が売電する際に環境価値が国に帰属し、それを証書として分離・販売します。
全量にトラッキング情報が付与されるため、RE100など国際的な基準にも対応可能です。
トラッキングについては下の項目で別に説明します。
また、FITに基づいて発電された電力の環境価値がなぜ発電事業者に帰属せず、国に帰属するか、という点についてですが、FITでは再エネ電気を電力会社が固定価格で買い取る際、国(正確には国が指定する電力広域的運営推進機関OCCTO)が買取費用を賦課金として国民から回収しており、環境価値も国民全体の負担によって成立すると位置付けられ、発電事業者ではなく国に帰属させる仕組みになっています。
非FIT非化石証書(再エネ指定あり)
FIT制度の対象外ですが、再生可能エネルギーに該当する電源(例:卒FIT電源、大型水力発電など)から発電された電力の環境価値を証書化したものです。
発電事業者の同意がある場合にはトラッキング情報が付与され、再エネ由来であることを証明する用途に利用されます。
3. 非FIT非化石証書(再エネ指定なし)
原子力発電など、再生可能エネルギーではないが化石燃料を使用しない電源からの電力に付随する環境価値を証書化したものです。
この証書にはトラッキング情報が付与されず、再エネ使用の証明には適していません。
RE100など国際的基準には対応していないため、使用には注意が必要です。
トラッキングの重要性
あらためて整理すると、トラッキング付非化石証書となりうるのは、第一にFIT非化石証書です。
これは2021年以降すべての証書にトラッキングが義務付けられており、RE100など国際基準に完全対応できます。
第二に非FIT非化石証書(再エネ指定あり)があり、2021年8月以降は発電事業者の同意がある場合にトラッキング情報を付与することが可能となりました。
一方で、非FIT非化石証書(再エネ指定なし)にはトラッキングが付与されず、国際基準に対応できない点で明確に区別されます。
トラッキング付非化石証書には、電源種別、発電所名、発電日などの詳細情報が付与されます。
これはRE100、Carbon Disclosure Project(CDP)、The Science Based Targets initiative(SBTi)など国際的な開示基準に対応するための必須条件となることが多く、特にグローバル企業ではこの有無によって報告の信頼性が左右されます。
トラッキングは、証書の裏付けとして「どの発電所で」「いつ発電されたか」といった属性を明確に示すため、単なる数字上のCO2削減ではなく、再エネ利用の実態を証明する役割を果たします。
また、監査や第三者レビューの際にも、トラッキング情報の有無が評価の分かれ目となることが多いのが現実です。
非化石証書の購入方法
非化石証書は主に3つのルートで購入できます。ここでは、それぞれの方法の特徴や注意点をより詳細に説明します。
JEPX市場取引(オークション方式)
日本卸電力取引所を通じた入札形式での取得となります。
毎月定期的に開催され、価格は需給バランスによって決定されることになります。
参加主体は小売電気事業者や大規模需要家が中心であり、購入結果は公開されるため価格の透明性が高いのが特徴ですが、取引参加には事前登録が必要であり、取引単位や入札のルールを理解しておく必要があります。
相対取引
小売電気事業者などと直接交渉して購入する方法となります。
長期の電力購入契約(PPA)に非化石証書を組み込むケースもあり、企業が自社の中長期的な脱炭素戦略に沿った調達を行うことが可能です。相対取引は市場よりも低価格で調達できる場合がある一方で、契約条件や証書の発行年度などを相手方と個別に調整する必要があります。
契約の自由度が高い反面、証書の有効性やトラッキング対応状況を確認することが不可欠と考えられます。
二次取得(転売)
既に取得済みの証書を他の事業者から譲り受ける方法です。
オークションや相対取引よりも簡便に入手できる場合がありますが、発行年度や使用期限、トラッキング情報の有無に注意する必要があります。
特に国際基準への適合を目的とする場合には、古い年度の証書やトラッキングなし証書では要件を満たさない可能性があります。
そのため、購入時に証書の属性を厳密に確認することが重要です。
活用メリットと注意点
メリット
以下、非化石証書を導入することで得られる主な利点を整理します。
各メリットの背景と活用効果を理解することで、自身にとって最適な活用方法や検討手順を明確にできるようになるものと考えます。
Scope 2排出量の削減に活用可能
GHGプロトコルの「Scope 2 Guidance」は、品質基準(Scope 2 Quality Criteria)を満たすエネルギー属性証書(EAC)を用いる場合に、市場ベースの算定で当該電力量の排出係数を0として扱えることを明確にしています。
したがって、トラッキング付かつ再エネ由来の非化石証書を適切に償却(無効化)すれば、企業は市場ベースのScope 2排出量を実質ゼロとして算定できます。
この際に求められる品質基準には、供給地域の市場境界の一致、発電と使用の時間整合(ビンテージ)、請求のダブルカウント防止などが含まれます。
初期投資を抑えて短期間で導入可能
非化石証書は物理的設備の設置を伴わず、購入と償却の手続を標準化することで短期間に導入できます。
一般論として、オンサイト発電やオフサイトPPAに比べて初期投資や工期、系統接続の制約に左右されにくいため、複数拠点への横展開を機動的に進めることが可能です。
RE100対応の要件を充足可能
RE100の技術要件は、地域の市場境界と時間整合に沿ってトラッキング付の再エネ由来証書を購入・償却することを求めています。
日本国内での使用については、日本市場で発行された再エネ指定ありの非化石証書を用いることで、要件に沿った実績として報告できる可能性が高まります。
二重計上を防止し監査対応を強化可能
証書の償却・無効化を適切に実施し、その記録を保持することで、同一電力量の二重計上を防止することが可能となります。
RE100は償却確認を重視しており、2026年使用分から償却確認の徹底が義務化される予定であるため、監査対応の観点でもメリットがあります。
市場価格の透明性を活かした戦略的調達が可能
JEPXの非化石価値取引市場では、開催予定や入札結果、約定価格帯などの情報が公開されています。
これにより、調達のタイミングや価格レンジを把握しやすくなり、証書調達の予算管理や戦略設計を合理的に行うことができます。
政策目標達成への貢献
非化石証書の活用は、小売電気事業者に課されている2030年度に非化石電源比率44%以上という政策目標の達成にも資するものであると考えられます。
企業が証書を通じて非化石電源の価値に価格を付けることは、電源構成の転換を市場メカニズムで後押しする効果を持ちます。
注意点(実務での落とし穴)
非化石証書購入前に知っておくべき制度上の注意点や、運用・報告の現場で起こりがちな問題を整理しておくことで、導入後のトラブルや手戻りを防ぎ、社内外への説明負担を減らすことが可能と考えられますので、非化石証書を実際に活用する際に陥りやすい課題やリスクについても以下説明していきます。
「再エネ指定なし」はRE100等の主張に不向き
原子力等を含む非FIT(再エネ指定なし)にはトラッキングが付かず、再エネ利用の主張やRE100対応には原則使えない点には注意が必要です。
時間整合(ビンテージ)の配慮
GHGプロトコルは「できるだけ近い時期」での整合を求めており、実務では原則同年度内の発電分で揃えるのが無難です(参照: GHG Protocol Scope 2 Guidance)。
地理的整合(市場境界)の配慮
RE100は同一市場内での調達・使用を基本とし、越境時は追加要件がかかるため、日本での使用には日本市場の証書を選ぶのが確実だと考えます。
二重計上のリスク管理
同じ電力量に対して複数の主張がなされないよう、証書の所有・移転・償却の記録と証憑の保管を徹底する必要があります。
デュアルレポーティングの必要
GHGプロトコルはロケーションベースと市場ベースの両方の開示を求めるため、証書で市場ベースを低減しても、ロケーションベースは系統平均係数で別途開示が必要です(参照: GHG Protocol Scope 2 Guidance)。
評価の行方(社会的議論)
証書活用の有効性を巡る議論はまだ継続中であり、SBTiもScope 2の扱いを巡る論点整理や見解を公表しています。将来の更新が報告・コミュニケーションに影響し得るため、最新のルールや解釈の動向を継続的に確認する必要があります。
他の環境価値証書との比較
以下の表では、非化石証書、グリーン電力証書、J-クレジットの三つについて、対象、トラッキングの有無、国際基準への適合度、主な用途の観点から横並びで比較しています。
まず全体像を把握し、そのうえで自身の報告目的(GHG排出量の算定やRE100対応など)とコミュニケーション目的(ブランドやCSRの発信など)を切り分けて検討することで、状況に応じた最適な証書を選定しやすくなるものと思われます。
| 証書名 | 主な対象 | トラッキング | 国際基準対応 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 非化石証書 | 非化石電源全般 | 有/無 | 条件付き | CO2削減報告、電力調達証明 |
| グリーン電力証書 | 再エネ(FIT外) | 有 | 一部対応 | ブランディング、CSR報告 |
| J-クレジット | CO2削減量 | 無 | 対応 | カーボンオフセット |
非化石証書の特長は、環境価値の取引を通じて「脱炭素に貢献する意思」を市場で可視化できる点にあります。
ただし再エネ指定の有無やトラッキング情報の有無により国際的な通用度が変わるため、目的に応じた適切な選択が必要だと思われます。
まとめ
非化石証書は、再エネ調達と温室効果ガス報告を現実的なコストで前進させる実務的な選択肢です。
まだ非化石証書に関わったことがない場合は、まずは最新の制度改定や実務上の定義を、自身の前提(対象年度、時間整合、地域の市場境界など)と照らして一次資料で確認することをお勧めします。
特に、資源エネルギー庁・OCCTO・JEPXの公開資料や、GHGプロトコルおよびRE100の技術要件の最新版を見直すことで、用語や適用範囲の誤解を避けることが可能となります。
この確認を踏まえて、自社の目的や制約条件を整理すると、次に検討すべき調達ルートや運用設計の論点が明確になるものと思われます。






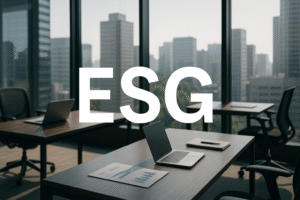


コメント