ざっくり言うと
-
日本のEV充電規格はJ1772とCHAdeMOが現時点では標準で、都市部ではインフラも急速に整備中
-
自宅充電や急速充電による日常利用は実用性が高く、コスト面でもガソリン車より有利
-
地方や長距離移動には課題も残るが、利用環境次第で今のEV購入は十分に現実的
はじめに:今、日本でEVを買うのは賢い選択なのか?
今回はESGや再生可能エネルギーといったトピックと若干離れますが、EV(電気自動車)の購入タイミングについて考えてみたいと思います。
実は、私は、2025年7月、インドネシア・ジャカルタに出張してきました。
その際、中国電気自動車メーカーのBYD製の電気自動車を非常によく見かけ、衝撃を受けました。
昨年2024年にジャカルタに訪問した際にも韓国ヒュンダイと中国ウーリンの電気自動車がジャカルタの街を走っていることに驚愕しましたが、今回の衝撃も同じくらいのものでした。
日本でもテスラを中心に、電気自動車を街でよく見かけるようになりました。
ただ、感覚的にまだ使い勝手が悪いのでは…などと思う方も多いのではないかと思われるため、今回検討してみようと考えました。
日本におけるEVの充電規格とその整備状況を網羅的に解説するとともに、都市部・地方部での実用性や、現在の充電技術の成熟度など、なるべく多角的に「今EVを買うことが勧められるのか?」という点を考えてみます。
使用パターンや住環境によってその答えは異なりますが、EV購入を検討する際の参考になれば、と考えています。
日本のEV充電規格の技術的特徴と標準化状況
まず、EVについては、ちゃんと充電できるの?というところが大きな心配事というか、関心事だと思われますので、この規格について説明してみます。
大きく「J1772」、「CHAdeMO」と、テスラが採用する規格である「NACS」 (North American Charging Standard)がありますので以下説明していきます。
J1772:普通充電の国内標準規格
日本において、普通充電用の標準規格として広く普及しているのが「J1772」です。この規格は日本および北米で共通して採用されており、国内で販売されているバッテリーEV(BEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)は基本的にJ1772に対応しています。
J1772の普通充電器は、交流(AC)100Vまたは200Vの電圧を使用し、出力は3kW~6kWの範囲が一般的です。
この電圧帯は家庭用電源と互換性があるため、設置工事が比較的簡単で済むという利点があるところが大きな特徴です。
普通充電は導入コストの低さが大きなメリットになります。
一般消費者にとってはこれが非常に大きいように思います。
コンセント型であれば数千円程度から設置が可能であり、普通充電器本体でも15万円から60万円程度で導入できます。
これは急速充電器の数百万円という価格帯と比較すると、格段に低コストです。
そのため、自宅や事務所、宿泊施設など、長時間駐車する場所への設置が進み、基礎的な充電インフラとしての地位を確立している、というのが現在の状況です。
CHAdeMO:急速充電の国際標準
急速充電分野においては、日本が主導して策定した「CHAdeMO」(チャデモ)規格が国内外で広く採用されています。
この規格は2010年に標準化され、現在では世界112カ国以上で約61,000基が設置されており、国際的にも認知度の高い充電規格となっています。
CHAdeMOの特徴として、最大出力400kWの直流電気を供給できる能力が挙げられます。
この方式では、充電器内で交流電力を超高圧の直流電力に変換し、EVのバッテリーに直接送電します。
この規格は継続的にアップデートされており、2018年には最大電圧が1000Vまで拡張されて400kWの出力が可能となり、さらに2021年には最大出力900kWへの対応が進められています。
このような技術革新により、大容量バッテリーを搭載する将来のEVにも対応可能なインフラが整備されつつあります。
NACS:おそらく今後の世界標準
NACSは当初テスラ独自の規格だったようですが、その後、標準化を目指す動きから名称を変更し、NACSと称するようになったようです。
充電口の小ささから利便性が高く、日本メーカーを含むEVメーカーがNACSを採用するとする動きが強まっています。
なお、日本国内で販売されているテスラ車は、他の車両とは異なり独自の充電口を採用していることが特徴です。テスラ車は一つの充電ポートで普通充電と急速充電の両方に対応しており、利便性が高い構造となっています。
しかし、日本の標準的な充電器を利用する際には、専用のアダプターが必要となります。
これには普通充電用と急速充電用の2種類があり、状況に応じて使い分ける必要があります。
2025年6月時点で、日本国内におけるテスラ専用のスーパーチャージャーは132カ所、合計669基が設置されているとのことです。
互換性 – アダプターがあれば互換可能
上記のとおり、様々な充電規格があるようですが、アダプターを使うことで別の規格の充電口を利用することができるため、充電規格の違いで利用に支障がでることはないのではないかと思われます。
また、NACSの点でお伝えしたとおり、今後はNACSで統一されていくのかもしれない、というように推測される情報をよく目にするようになっています。
マツダが日本国内向けEVにNACS採用を発表〜2027年以降発売の電気自動車に搭載
全国のEV充電インフラ整備状況と地域格差
GoGo EVによれば、2024年12月末時点で、日本国内に設置されているEV充電スポット数は24,592拠点に達しています。
これは2023年3月の時点での19,764拠点から、約1年9ヶ月で4,828拠点、率にして24.4%の増加を示しており、充電インフラが着実に拡大していることがわかります。
内訳を見ると、CHAdeMO規格の急速充電器が11,804口、200Vの普通充電器が31,432口、100Vの普通充電器が204口、そしてテスラ専用の充電器が954口となっており、普通充電器の展開数が急速充電器の約2.7倍という規模感です。
普通充電器の方が導入コストが低い、という点からも頷ける内容だと考えられます。
なお、政府は2030年までに充電インフラを30万口設置するという目標を掲げており、現在の設置ペースをさらに加速させる必要があります。
これに対応するため、国や地方自治体は補助金制度や技術開発支援、さらには民間事業者との協業を通じた施策を展開しています。
都道府県別の設置状況をみると、東京都が最多で2,665基の200V普通充電器と860基のCHAdeMO急速充電器を有し、全国で最も充電インフラが整備されています。
これはなんとなく想像がつくところかと思います。
次いで愛知県(普通1,952基・急速786基)、大阪府(普通1,612基・急速502基)が上位に位置しています。
一方で、地方部では充電インフラの整備が相対的に遅れており、例えば鳥取県では普通充電器が225基、急速充電器が90基という状況で、都市部との格差が顕著です。
また、施設別の設置状況を見てみると、急速充電器の設置場所として最も多いのがコンビニエンスストア、次いでショッピングモール・小売店、そして道の駅が続いています。
一方、普通充電器の設置場所としては、宿泊施設・温浴施設が最多で、次いでレジャー・スポーツ施設、ショッピングモール・小売店という順になっており、利用シーンに応じた設置傾向がうかがえます。
充電のしやすさと日常利用における実用性評価
充電時間と走行距離の関係性分析
EVの実用性を評価する上で、充電時間と走行可能距離の関係は極めて重要な問題だと思います。
例えば、一般的な200V普通充電(3.2kW)の場合、40kWhのバッテリーをゼロから満充電にするには約12.5時間を要するとのことです。
これは日産リーフのスタンダードモデル相当の数値であり、実際の走行距離に換算すると約250〜300kmに相当します。
もっとも、日常的な使用においては毎回満充電する必要はなく、通勤や買い物などで必要とされるのは1日あたり数十km程度で足りるのではないかと思われます。
例えば、40km分の充電であれば、200V普通充電器を用いて約2時間、6.0kW出力の高出力型普通充電器を使えば約1時間で済むとのことです。
急速充電器では、50kW出力の標準的な設備であれば約30分でバッテリーの80%程度を充電することが可能です。
この特性は高速道路のサービスエリアや都市間移動において極めて有用であり、実用的な選択肢となっています。
ただし、充電率が高くなるにつれて充電速度が低下する仕様上、実際の充電時間はバッテリー残量や車種によって前後することが考えられます。
経済性と利便性の比較評価
経済面で見ると、EVの充電コストはガソリン車と比較して明確な優位性を持っている、つまり、コスパがいいと考えられます。
月間800km(年間9,600km)の走行を想定した場合、ガソリン車では燃費14km/ℓ、ガソリン価格150円/ℓとして月額約8,570円の燃料費がかかります。一方、EVでは電費7km/kWh、電気料金35円/kWhと仮定した場合、月額は約4,000円となり、約53%のコスト削減が見込まれます。
2025年7月時点でガソリン価格はもう少し高いことが通常でしょうから、この差は更に広がっている、ということになります。
また、自宅に充電設備を設置する際のコストも比較的現実的な水準にあります。
コンセントタイプであれば20〜50万円程度、普通充電器では30〜100万円程度の初期費用で導入可能です。
集合住宅や事務所においては共用設備として設置することで、利用者間でのコスト分散が図れます。
利便性の面でも、EVは大きなメリットがあると思われます。
特に自宅での夜間充電が可能である点は、利用者にとっては、生活に支障なく使える、という点で大きなメリットです。
ガソリンスタンドに立ち寄る必要がなくなり、毎朝満充電に近い状態で出発できるという点は、日常利用における大きな魅力になるのでは、と思われます。
充電不安とその実際的な対策
EV購入に対する懸念の中でよく挙げられるのが「充電不安」です。
しかし、実際の利用状況を踏まえると、この懸念はそこまでのものではないと考えられます。
たとえば、EVは1kWhあたり6〜7kmの走行が可能であり、通勤距離が片道20km程度であれば、1日の充電量は10kWh以下で済む計算になります。
この程度であれば、夜間に自宅で充電すれば十分に対応可能です。
長距離移動に関しても、急速充電インフラの整備が進んでおり、高速道路などの主要ルートには30分程度の充電で次のスポットまで移動できる間隔で設置がなされています。
問題は地方や山間部で、充電スポット間の距離が長く、事前の充電計画が必要な場面もあるため、これらの地域で頻繁に移動する方にとっては、EV購入は利用する頻度や充電スポットの詳細な確認など、慎重な判断が求められることになると思われます。
このような充電不安を軽減するためには、充電スポット情報をリアルタイムで提供するシステムの活用が有効だと考えられます。
先ほど上で紹介した「GoGoEV」などの情報共有サイトを利用することで、現在地周辺の充電スタンドの稼働状況や位置情報を簡単に把握することができ、旅行や長距離移動時の計画に役に立つのでは、と思われます。
現時点でのEV購入の妥当性の評価
使用パターン別適正性分析
上で説明したところからも、EVを購入するのがいいのかどうかという判断は、利用者の居住地域や走行パターンによって大きく異なるように思われます。
例えば、都市部に居住し、日常的な通勤や買い物を主な用途とする場合、現時点でのEV購入は極めて合理的な選択だと考えられます。
自宅に普通充電設備を設置することで、ガソリンスタンドに立ち寄る手間が省け、充電コストも抑えられるため、経済性と利便性の両面で高い評価を得られます。
営業車や配送車などの業務用途でも、走行ルートが一定であり、消費電力が予測でき、拠点での充電が可能な場合にはEVを購入するという選択肢がより妥当であるように思われます。
特に都市部での短〜中距離の移動が中心となる業務では、環境性能の観点からもEVに優位性があります。
ただし、長距離輸送や山間部での頻繁な移動を伴う業務においては、現状のインフラでは実用性が制限される可能性があるため、慎重な検討が必要、ということになります。
一方、地方部に居住している場合や、長距離移動が多い生活スタイルを持つ利用者にとっては、EV購入には一層の注意が必要になります。
自宅で充電して、その充電分だけで移動が十分だ、という方は特に問題ないかもしれませんが、長距離移動が多いとなると、充電スポットを探すことにもストレスがかかってしまうのでは…と思われます。
充電インフラの整備状況に地域差があるため、移動の自由度が制限されるリスクがあります。
突発的な移動や緊急対応などを考慮すると、ガソリン車に比べて柔軟性に欠ける側面があるため、使用パターンとインフラの適合性を十分に検証することが必要になりそうです。
技術的観点からの購入タイミング評価
現在のEV充電技術は、規格面・性能面の両面で一定の成熟度に達しており、技術的に見ても「今買うこと」が不利とは言い切れない状況にあります。
たとえば、急速充電の国際標準であるCHAdeMO規格は、継続的なアップデートによって高出力化が進められており、最大出力900kWへの対応も可能になっています。
既存のEVでも、このような高出力の恩恵を一定程度享受できる設計となっており、購入後に陳腐化してしまうリスクはあまり考えなくても良いように思われます。
また、バッテリー技術においても年々改良が進められており、航続距離の延長や充電時間の短縮といった性能向上が見られます。
現行モデルの多くは、日常利用においては十分な性能を備えており、もはや「発展途上の技術」として警戒すべき段階を脱しているといえます。
政府も2030年の30万口設置目標に向けた政策支援を継続しており、こうした流れは今後さらに加速する見込みです。
以上のことから、技術的観点においてもEV購入は現実的な選択肢といえるでしょう。
経済的側面からの投資妥当性
EV購入を経済的に評価する際には、初期投資の回収期間と、運用コストの削減効果をバランスよく見極める必要があります。
一般に、EVはガソリン車よりも車両価格が高い傾向にありますが、燃料費の大幅な削減や、定期点検・部品交換の頻度が少ないことによる維持費の抑制など、トータルコストでは優位に立つのではないか、と推測されます(特に昨今のガソリン価格の高騰を踏まえるとよりそのように思われます)。
また、国や地方自治体が提供する補助金制度を活用することで、初期投資額を大きく軽減することが可能です。
購入時の補助金に加えて、充電設備の設置費用にも補助が適用される場合があり、制度をうまく活用すれば経済的負担を抑えることが可能です。
ただ、こうした補助金制度は予算や政策変更の影響を受けやすいため、最新情報を把握したうえでの計画的な購入が必要になろうかと思われます。
さらに、中古車市場におけるEVの価値保持についても検討が必要です。
EV技術の急速な進化により、将来的なリセール価格を正確に予測するのは難しく、投資としてのリスクが残るのも事実です。
一方で、各国で内燃機関車の規制が進む中で、長期的にはEVの資産価値が相対的に上昇する可能性も指摘されています。
今のところはリセール価格がガソリン車に比べて低い、という話も聞かれますので、この点はまだまだ、ということかもしれません。
結論:充電規格を基盤とした総合的購入推奨
以上から、今EVを購入してもいいか、するべきか、という点の結論は、「使用パターンと居住地域による条件付きで購入しても良い、購入するべき」ということになるのではないかと考えられます。
J1772およびCHAdeMOという確立された充電規格により、技術的な基盤はすでに整備されており、都市部を中心とした充電インフラの拡充も着実に進んでいます。
特に都市部に住んでいて、日常的な使用が中心である場合には、現時点でのEV購入はおすすめなのでは、と思われます。
自宅での充電環境を整備することで、利便性と経済性の両方のメリットを享受でき、「充電不安」も最小限に抑えることが可能です。
営業車や配送車などの用途においても、走行パターンが予測可能である限り、メリットがあるように思われます。
一方、地方部での居住や長距離移動が多い用途については、充電インフラの地域格差を十分に評価した上で購入を検討する必要がありそうです。
特に、突発的な移動や緊急対応が求められる場合には、充電スポットの配置や充電時間の制約が実際の運用に影響を及ぼす可能性があります。
ただ、政府のインフラ整備方針や、民間企業の投資による充電網の拡張も進んでおり、環境は確実に整いつつあります。
上記のとおり、EV購入は、一定条件で、現時点において十分な実用性と将来性を兼ね備えた合理的な選択であると結論づけていいように思われます。
購入を検討する際には、ご自身の利用環境やお住まいのエリア、補助金制度の内容を検討することが重要ではないかと考えます。
各社のウェブサイトをみたところ、ガソリン車に比べて極端に高いわけでもないように思われますし、私もEV購入を検討してみたいと思います。







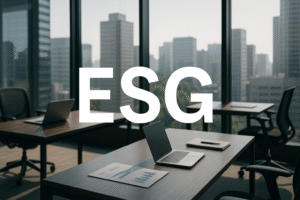


コメント