✅ ざっくり言うと
– 2030年ネイチャーポジティブ実現に向け、金融機関による投融資が加速。日本生命が科学的評価手法を公表
– NPP(植物の光合成で生産される炭水化物量)とHANPP(人間が利用する量)という指標で自然へのインパクトを定量化
– TNFD開示が進む中、企業は自然資本を成長戦略に結び付ける対話が求められる
はじめに
今回はネイチャーファイナンスの評価手法について説明していきます。
2025年10月、日経ESGに興味深い記事が掲載されました(「ネイチャーファイナンス」が加速)。
記事では、2030年までに自然の損失を止めてプラスに転じる世界目標「ネイチャーポジティブ」の実現に向け、金融機関が投融資を加速させている状況が報じられています。
特に注目すべきは、運用資産残高約80兆円の日本生命保険が2025年8月にネイチャーファイナンスの評価手法を発表した点です。
また、日本格付研究所(JCR)や格付投資情報センター(R&I)も同7~8月にネイチャーファイナンスの適格性の評価方法や指針を相次いで発表しており、ネイチャーファイナンスの実務的な枠組みが整いつつあることがうかがえます。
この動きの背景には、2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」があります。
GBFでは、2030年までに陸と海の30%以上を保全する「30by30目標」など23個の具体的なターゲットが設定され、その中でターゲット15では企業に対して生物多様性に関する影響評価と情報開示が、ターゲット19では年間2000億ドルの資金動員が求められています。
また、2023年9月には自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が最終提言を公表し、企業による自然資本に関する情報開示の枠組みが整備されました。
WWFジャパンの調査によれば、2025年7月時点でTNFD開示を表明した企業(TNFDアダプター)は世界で611社、うち日本企業は180社と世界最多を占めています。
こうした国際的な枠組み整備が進む一方で、企業の実務現場では「自然の回復に貢献する活動をどう評価するか」という根本的な課題が残されていました。気候変動分野ではGHG排出量という明確な指標がありますが、自然分野ではその複雑性から共通の評価尺度が確立されていなかったためです。今回、日本生命が公表した評価手法は、この課題に一つの解決策を示すものとして注目されます。
ネイチャーファイナンスとは何か
ネイチャーファイナンスとは、自然関連プロジェクトへの投融資を指します。
具体的には、ローン(融資)、インパクトファイナンス、ボンド(債券)などの形態で、森林保全・再生、生物多様性保全、生態系回復などのプロジェクトに資金を提供するものです。
この動きが加速した背景には、2024年から2025年にかけて国際的なガイドラインが相次いで発表されたことがあります。
責任投資原則(PRI)や国際資本市場協会(ICMA)が自然に関するガイドラインを公表し、ネイチャーファイナンスの実務的な枠組みが整備されてきました。
特にICMAは2025年6月に「Sustainable Bonds for Nature: A Practitioner’s Guide」を公表し、既存のグリーンボンド原則に加えて、自然関連プロジェクトに特化した実務ガイドを示しています。これを受けて、日本でもJCRとR&Iが評価方法を策定し、ネイチャーファイナンスの適格性を判断する仕組みが構築されつつあります。
従来のグリーンファイナンスが主に気候変動対策(再生可能エネルギー、省エネルギー等)を対象としていたのに対し、ネイチャーファイナンスは生物多様性保全や生態系回復という、より複雑で多様な要素を含む領域を対象とする点が特徴です。
日本生命の評価手法の画期性
日本生命が2025年8月に公表した「日本生命ネイチャー・ファイナンス・アプローチ」は、科学的合理性を備えつつ実用的でシンプルな指標として、NPP(Net Primary Production:純一次生産量)とHANPP(Human Appropriation of Net Primary Production:人間による純一次生産の収奪)という概念を採用した点が画期的です。
NPPとHANPPとは何か
NPPとは、地球上の植物が光合成によって生産する炭水化物の総量を指します。
植物は光エネルギーを使って二酸化炭素と水から炭水化物(糖など)を作り出しますが、植物自身もその活動に必要な分を消費するため、その分を差し引いたものがNPPとなります。
この炭水化物は食物連鎖の出発点となり、動物が植物を摂食し、その動物をさらに別の動物が摂食するという形で、生態系全体のエネルギー循環を支えています。
つまり、NPPは生態系における「生命を支えるエネルギー量」の指標と言えます。
一方、HANPPは、このNPPのうち人間活動が利用する量を指します。
産業革命前はNPPに対してHANPPは1.9%でしたが、2020年には23.5%に上昇し、HANPPは168億トンに達しました。
人口増加と経済成長に伴い、農地開発や都市化による森林伐採が進み、人間が利用できる自然のエネルギー量が増大している状況を示しています。
プラネタリーバウンダリーとの関係
日本生命がNPP/HANPPという指標を選択した理由の一つは、これらがストックホルム・レジリエンス・センターが提唱する「プラネタリーバウンダリー(地球の限界)」の概念と整合している点にあります。
プラネタリーバウンダリーは、人類が安全に活動できる地球環境の限界を9つの領域で示したものですが、その一つである「生物圏の一体性(Biosphere Integrity)」において、HANPPを年間56億トンに抑えることが目標として示されています。つまり、企業がHANPPを減らす活動は、直接的に地球規模目標の達成に貢献することになります。
具体的な測定方法
日本生命の評価手法では、NPPの増加やHANPPの低減を、NASA(米航空宇宙局)が公開しているNPPデータと地理情報システム(GIS)のソフトウェアを活用して測定します。
例えば、パーム油を調達する食品メーカーが調達先の小規模農家の生産性向上を支援することで、農地拡大のための森林伐採を抑制できます。
この場合、森林抑制面積にNPPデータを乗じることでHANPPの回避量を算出できます。
生物種の個体数については、投融資前に実測し、活動後にどれだけ増えるかを森林管理計画や人工知能(AI)で推計します。投融資後は約3年ごとに測定し、実際の効果を検証する仕組みです。
適格事業の類型
日本生命の評価手法では、以下の事業がネイチャーファイナンスで適格とされます。
NPPを増やし生物の個体数を増やす活動
– 森林保全・再生事業
HANPPを減らす活動(森林伐採抑制事業)
– 農地や放牧地の拡大を抑制する事業(農業の生産性向上、代替タンパク質の開発等)
– サプライチェーン上流で森林伐採を伴う原材料の調達を抑える事業(鉱物や天然ゴムの再利用、パーム油の代替原料開発等)
– 途上国での都市化による森林伐採を抑制する事業(高層集合住宅の開発等)
企業にとっての実務的意味
TNFD開示との関係
TNFDは企業に対して自然への依存、インパクト、リスクと機会を開示することを求めていますが、WWFジャパンが2024年の日本企業65社の開示状況を調査したレポートによると、多くの企業がENCOREのようなツールを活用した一般論の分析結果にとどまっており、場所に基づいた「自社と自然との」具体的な依存・影響関係を分析できている開示は一部の企業に限られていました。
日本生命の評価手法は、こうした企業の課題に対して、具体的なプロジェクトの自然へのインパクトを定量的に示す手段を提供するものといえます。
企業は自社の活動がNPPの増加やHANPPの減少にどれだけ貢献するかを測定することで、TNFD開示における「自然の状態(State of Nature)」に関する指標の一つとして活用できる可能性があります。
資金調達への影響
ネイチャーファイナンスの評価手法が確立することで、企業は「ネイチャーボンド」や「ネイチャーリンクローン」といった資金調達手段を活用しやすくなります。
R&Iのサステナブルファイナンス本部副本部長の石渡明氏は、「ネイチャーボンドやネイチャーリンクローンについて金融機関から問い合わせがある」としつつも、「自然の活動を会社の成長戦略に関連付けたり、活動とインパクトをひも付けるのが難しい」と指摘しています。
日本生命の宮下雄一責任投融資推進室担当課長は、「今回ネイチャーポジティブに近づくための評価尺度を示した。日本生命がこういう活動に投融資することを打ち出したことで、企業に活動のインセンティブを与えられる」としています。
サプライチェーン管理の重要性
特に食品・製造業など、自然資本に依存度の高い業種にとって、サプライチェーン上流での対応が重要になります。
パーム油、天然ゴム、木材などの調達において森林破壊を伴わない方法を選択することが、HANPPの削減につながります。
上記のWWFジャパンのレポートでは、花王株式会社がバリューチェーン上流のトレース状況を開示した事例や、パーム調達に関する苦情受付体制を整備した事例が、優れた開示として紹介されています。
今後の課題と展望
日本生命の宮下課長は、「測定・評価手法はまだ最終形ではない。企業との対話を通じて改善していく」と述べています。実際、森林ファンドを運用する海外の運用会社が、2026年を目指して指標と評価手法の採用を検討中であり、既に生物の個体数を測定しているとのことです。
企業側にとっても、R&Iの石渡氏が指摘するように、「自社の成長戦略と自然の関係を整理し、金融機関と対話を進めることが重要」です。それがネイチャーポジティブ経営への正しい評価を生み、資金の呼び込みにつながります。
WWFジャパンの小池祐輔専門オフィサーは、「TNFD開示は、本来、自然関連課題の分析を通じて、自然に負荷をかけるビジネスモデルを根本から変革する契機となることが期待されています」と述べており、企業には単なる情報開示にとどまらない、事業モデルそのものの変革が求められています。
まとめ
ネイチャーファイナンスは、評価手法の確立により実務的な展開期に入ったといえます。
日本生命が提示したNPP/HANPPという指標は、科学的な裏付けを持ちながらも実用的でシンプルな尺度として、企業と金融機関の対話を促進する役割が期待されます。
TNFD開示を表明する日本企業は世界最多の180社に達していますが、WWFジャパンの調査が示すように、開示の「質」の向上が今後の課題です。企業は「守り」(リスク管理)だけでなく「攻め」(成長機会)の視点から、自然資本を経営戦略に統合していく必要があります。
2030年のネイチャーポジティブ実現という目標まで、残された時間は限られています。企業、金融機関、格付機関、そして国際機関が協力しながら、評価手法の改善と実践を重ねていくことが、自然の回復と持続可能な経済成長の両立につながるものと考えられます。
私も再エネ・ESG分野の実務に携わる者として、この動きを注視し、企業の皆様へのアドバイスに活かしていきたいと思います。
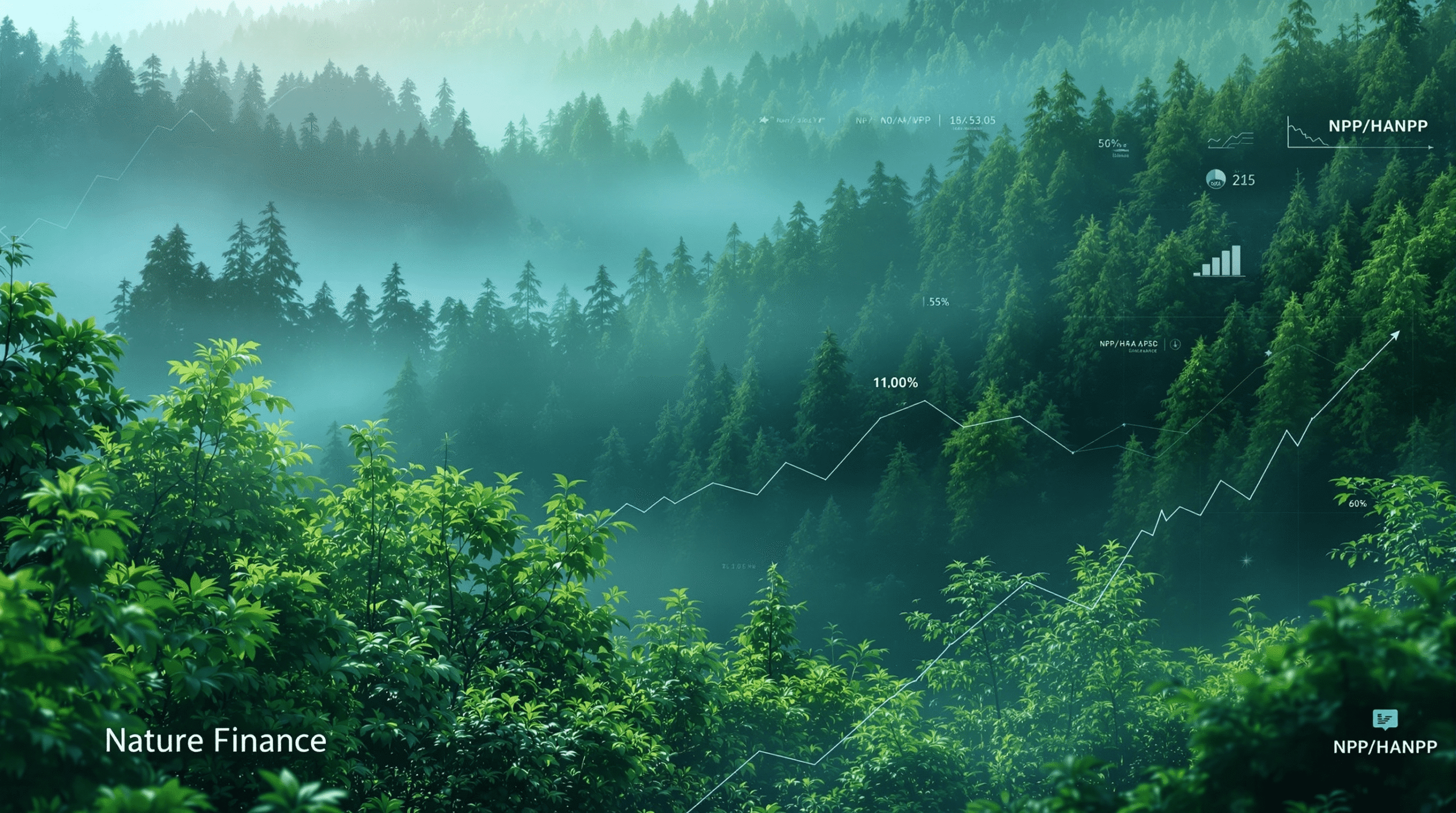





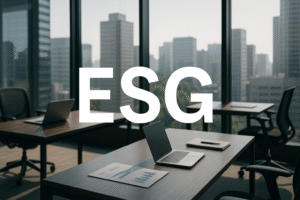


コメント