はじめに
今回は国産のSAF(Sustainable Aviation Fuel)について説明していきます。
2025年7月、東京国際空港(羽田空港)で国産SAFが定期旅客便に給油され、日本の航空業界は脱炭素化へ向けて歴史的な第一歩を踏み出しました。
羽田空港では、日揮ホールディングス・東京都・全日本空輸(ANA)・日本航空(JAL)が共同で推進する「Fry to Fly Project」(若干ダジャレっぽい気が…)により、家庭や店舗から回収した廃食用油を原料とする国産SAFが定期便に給油されました。
回収・製造・輸送・給油という一連のサプライチェーンを国内で完結するスキームは日本初であり、国産SAFの商業運用モデルとして注目を集めています。
SAFについては以前も取り上げたことがありますので、よろしければご覧下さい。
国内におけるSAFの最新動向と展望 (SAFへの投資に興味がある方を想定して書いています)
SAFの原料・製造プロセスと原料偽装問題
東京都の国産SAF利用促進事業
東京都は全国で初めて、国産SAFと従来ジェット燃料の価格差を補填する「国産SAF利用促進事業」を創設しました。
同制度は1リットル当たり100円、年間250万リットルを上限とする補助金を交付し、第1号採択事業者としてコスモ石油マーケティングを選定しました(東京都プレスリリース 2025年5月7日)。
この政策は航空各社のSAF導入コスト負担を軽減し、羽田空港における安定的なSAF利用の継続を後押しするものと考えられます。
技術革新と製造拠点の最新動向
大阪府堺市のコスモ石油堺製油所内では、SAFFAIRE SKY ENERGYが年間約3万キロリットルのSAFを生産する国内初の大規模製造設備を建設し、2024年12月に稼働を開始しています。
同設備は100%廃食用油を原料とし、ISCC CORSIA認証およびISCC EU認証を取得済みで、国際的持続性基準を満たしているとのことです。
今後はさらなる能力増強と原料多角化によるコスト低減が期待されるところです。
市場規模と政府目標
世界のSAF市場規模は2023年時点で約12億6,200万米ドルと推計され、2030年には138億4,120万米ドルに達し、年平均成長率はおよそ60%に上る見通しです。
一方で、日本政府は2030年までに国内ジェット燃料消費量の10%(約172万キロリットル)をSAFに置き換える目標を掲げており、供給見込みは192万キロリットルとされています。
今のところは十分な供給を見込んでいる、ということになりそうです。
普及を阻む三つの壁
上記のとおり、SAFに関しては皆さんの関心が高まってきているところではありますが、まだまだ課題も抱えています。
大きなところは以下の3点と考えられます。
認知度の低さ
国土交通省が2024年に実施した調査では、SAFを「よく知っている」と回答した消費者は19.0%にとどまり(PDF28ページ参照)、半数以上が「聞いたことがある程度」または「知らない」と回答しています。
この分野は日を追うごとに関心も高まると思われますので、現時点では「よく知っている」と回答する方も増えている可能性はあります。
高コスト
現在のSAF価格は1リットル当たり200〜1,600円と従来燃料(約100円)の2〜16倍であり、航空各社にとって大きな負担となり得ます。
原材料理解の不足
SAFの主原料が廃食用油であることを認識している回答者は44.7%に過ぎず、循環型資源としての価値が十分に浸透していません。
官民協働による解決策
政府は経済産業省と国土交通省が共同で官民協議会を設立し、需要創出とサプライチェーン強化に向けた工程表を策定しました。
具体的には、製造設備への補助金(約360億円)や税制優遇、値差補填によって価格競争力を高めるとともに、地方自治体とも連携し廃食用油の回収体制を整備しています。
国際的な取り組みとの比較
欧州連合(EU)ではReFuelEU Aviation規則により、2025年に2%、2030年に6%、2050年までに70%のSAF混合義務化が段階的に導入される予定です。
米国はSAF Grand Challengeで2030年に年間30億ガロン(約1.14億キロリットル)の供給目標を掲げ、小規模空港の設備費用の90%を助成するなど積極的な政策支援を実施しています。
技術開発のフロンティア
現行主流のHEFA(廃食用油や動植物油脂由来)に加え、アルコール to ジェット(ATJ)や都市ごみガス化FTプロセス、藻類由来SAFなど、多様な原料・技術が実証段階にあります。
これら次世代技術の商業化は原料の確保とコスト削減に直結し、2030年以降の安定供給体制の鍵を握るものと考えられます。
循環型社会への貢献と消費者の役割
我々消費者としてもSAFに関して貢献できることがあります。
SAFは単なる化石燃料代替ではなく、循環型経済の中核を担う存在ともいえます。
家庭や事業所から排出される廃食用油を回収・再利用することで地域経済の循環を促し、食品ロス削減にも寄与します。
消費者は廃食用油の適切な分別回収に協力し、SAF使用便を選択することで普及を後押しできます。
今後の展望と結論
羽田空港での国産SAF供給開始により、日本の航空業界は脱炭素化への道筋を明確にしました。
しかし、上で課題であると説明しました、認知度向上、コスト削減、原料確保という三つの壁を乗り越えるには、政府・産業界・自治体・消費者が一体となった取り組みが不可欠だと考えられます。
東京都の先駆的支援制度が全国に波及し、価格差補助が広域的に整備されれば、2030年の10%導入目標は現実味を帯びるのでは、と考えます。
日本は、羽田や成田をハブ空港にするという点は、シンガポールのチャンギ空港などを見ますと必ずしも成功しているとは考えにくいのですが、SAFについては、日本がSAFハブとしてリーダーシップを発揮し、新たな空の時代を切り開くことが期待されます。







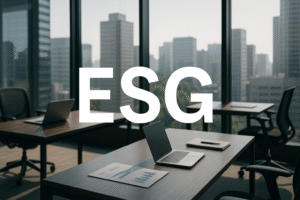


コメント