✅ ざっくり言うと
🔊 蓄電所の騒音、太陽光の反射光──依頼者との雑談から生まれた記事テーマ
⚖️ 裁判事例多数: 風力の低周波音、反射光で室温50℃、景観権は認められず
📜 145以上の自治体が独自条例で規制、国もガイドライン整備を加速
🤝 事業者の対策と地域還元策がカギ──法律と対話の架橋が必要
はじめに – 依頼者との雑談から
先日、依頼者と雑談している中で「蓄電所って、容量が大きくなると騒音も大きくなるんですよね」という話を聞きました。
再生可能エネルギーというと太陽光パネルや風車ばかりがイメージされがちですが、系統安定化のために欠かせない大型蓄電設備にも「音」という問題があることに改めて気づかされました。
実は今、太陽光発電所や風力発電所が全国各地に広がるにつれ、周辺住民との間で様々な摩擦が生じています。
騒音、低周波音、太陽光パネルの反射光による眩しさ、景観の悪化、さらには森林伐採に伴う土砂災害リスク…
こうした問題は、単に技術的・経済的な視点だけでは解決できません。法律家としても、また地域社会の一員としても、この問題は他人事ではないと感じています。
実際に起きている地域トラブル
風力発電の騒音訴訟(愛知県田原市)
住宅から約350メートルの場所に建設された1,500kWの大型風車。住民は「受忍限度を超える騒音だ」として事業者を提訴しましたが、2015年4月の判決では「法的許容範囲内」として請求棄却。
法的には許容範囲であっても、実際に近隣で暮らす人々の感覚は別問題です。
秋田県由利本荘市など風車が林立する地域では、低周波音による健康被害を訴える住民が後を絶ちません。
太陽光パネルの反射光で熱中症(兵庫県姫路市)
住宅近隣のメガソーラーから反射した強烈な日光により、室内温度が50℃以上に上昇。夫婦が熱中症になったとして2015年に提訴された事例です。
この件では、企業側が自主的に高木を植えて遮蔽対策を講じ、2017年に住民側が訴えを取り下げる形で決着しています。
企業の柔軟な対応が、裁判の長期化を防いだ好例といえます(一応)。
景観破壊を巡る訴訟(大分県由布市湯布院町)
高原景勝地へのメガソーラー計画に対し、旅館経営者ら住民が「地域の自然景観を享受する人格的権利が侵害される」として開発差し止めを求めました。
しかし2016年11月、大分地裁は「景観利益は法的保護に値する利益に留まり、環境権・景観権を直接根拠とする差し止め請求は認められない」として訴えを棄却。
景観を巡る争いは、法的には住民側が敗訴するケースが多いのが実情です。
森林伐採と土砂災害リスク
奈良県平群町では2021年3月、約1,000人の住民が「森林伐採で山がハゲ山になり土砂災害が心配だ」として事業者を相手取り発電計画の差し止めを集団提訴。
岡山県赤磐市では、82ヘクタールに及ぶメガソーラー造成後に斜面崩落が発生し、麓の水田が土砂で埋まる実害も出ています。
国・自治体の対応と事業者の工夫
145以上の自治体が独自条例を制定
国の調査によれば、強い規制要素を持つ太陽光条例を制定した自治体は全国で145件以上(届出義務のみを含めると約175件)。
全自治体の約1割が独自条例で対応している状況です。
埼玉県日高市では2019年、森林保全区域・観光拠点区域などの特定保護区域内では太陽光発電を許可しないとする条例を制定。
事業者が違憲訴訟を起こしましたが、2022年5月にさいたま地裁は訴えを却下し、条例の適法性が確認されています。
事業者側の創意工夫
一方で、地域との共生を図る事業者の取り組みも進んでいます。
- 低騒音型機器の採用と防音壁の設置
- 防眩パネルや反射光シミュレーション
- 積極的な緑化と景観への配慮
- 住民説明会の複数回開催と苦情窓口の設置
- 売電収入の一部を地域に還元する協定締結
青森県中泊町の風力発電所では、町と「地域再生のための寄附協定」を締結し、売電収入の一部を歴史的建造物の保存整備や福祉健康センター建設などに充当しています。
詳細は法律事務所コラムで
今回、この問題について実際の裁判事例、国や自治体の制度対応、事業者側の具体的な対策を網羅的にまとめた長文コラムを、所属する法律事務所のサイトに掲載しました。
再生可能エネルギー施設と地域トラブル – 騒音、反射光、そして住民との共生を考える
以下のような内容を詳しく解説しています。
✅ 各地の裁判事例の詳細(判決の法的論点、住民・事業者双方の主張)
✅ 環境省の騒音規制基準、国交省の反射光対策ガイドライン
✅ 自治体条例のゾーニング手法と違憲訴訟の結果
✅ 事業者の防音・防眩・緑化対策の具体例
✅ ADR(裁判外紛争解決)の活用可能性
✅ 地域経済への還元策と市民共同発電の仕組み
再エネ事業者の方、自治体の環境・都市計画担当者の方、周辺住民として不安を感じている方にとって、実務的に役立つ内容になっていると思います。
おわりに
「法的に勝った」ことが、必ずしも「問題が解決した」ことを意味しないのが、この分野の難しさです。
再生可能エネルギーの導入拡大は、脱炭素社会の実現に不可欠です。
しかし、その過程で地域社会との摩擦を生んでしまっては本末転倒と言えるでしょう。
制度面の整備と事業者の創意工夫によって、多くのトラブルは予防・解決できると考えられます。
最前線では事業者と住民・行政が膝を突き合わせた対話と工夫が不可欠です。
弁護士として地域トラブルに向き合う立場からも、技術と法律、そして人と人との対話を架橋する役割を果たしていきたいと思います。






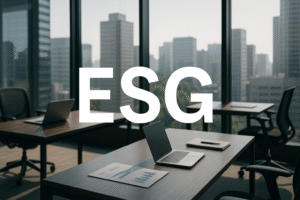


コメント