✅ ざっくり言うと
- 💰 日本のエネルギー自給率はG7最低の15.3%、年間24兆円もの国富が化石燃料輸入で流出する構造的課題に直面しており、再エネの「量」だけでなく「質」の主力電源化が急務となっています
- 🔄 2026年度からFIT電源よりFIP電源を優先する出力制御ルールが導入され、既存FIT事業者の収益構造に影響するため、プロジェクトファイナンス契約の見直しや金融機関との事前協議が必要になるケースが想定されます
- 🏘️ 非FIT/非FIP事業も「再エネGメン」監視対象に拡大され、全ての太陽光発電事業に対する法令遵守体制が強化されており、事業者にはコンプライアンス体制の抜本的見直しが求められています
- 🔬 ペロブスカイト太陽電池(PSC)は2040年までに累積20GW、発電コスト10〜14円/kWh以下を目標とし、需要地近接設置による地域共生と導入拡大の両立に貢献すると期待されますが、商用化までの長期戦略であり短期的な事業判断には慎重な見極めが必要です
✅ 「総合資源エネルギー調査会・再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第77回)」の配布資料をまとめた音声はこちら
はじめに
今回は、2025年11月12日に開催された総合資源エネルギー調査会・再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第77回)の配布資料を基に、日本のエネルギー政策の中核である再生可能エネルギー(以下「再エネ」)の「主力電源化」戦略について、弁護士としての実務的視点から解説していきます。
我が国は、使用可能な天然資源が乏しく、エネルギー供給の大部分を海外からの化石燃料輸入に依存しているという構造的脆弱性を抱えています。
具体的には、年間24兆円もの国富が化石燃料の輸入で海外に流出しており(資源エネルギー庁「資料1」p.8)、日本の一次エネルギー自給率はG7で最低水準の15.3%にとどまっています(同p.6)。
このエネルギー安全保障上の課題は、国家の持続可能性にとって喫緊のテーマであることは疑いの余地がありません。
こうした背景を踏まえ、エネルギー安定供給と脱炭素化を両立させるために、再エネの最大限の導入が求められています。
ただし、ここでいう「主力電源化」とは、単に発電量(kWhベース)を増やすことだけを意味するものではありません。FIT(Feed-in Tariff)/FIP(Feed-in Premium)制度などの政策支援から自立し、一般の発電事業と同様に電力市場の需給に応じた供給を行うなど、質的にも高度に進化した電源となることを目指すものであると考えられます(同p.2)。
再エネ事業に携わる事業者様、そしてESG(Environment, Social, and Governance)経営を推進する企業の皆様にとって、日本の再エネ政策が今後どのように進展するのかは、投資判断や事業戦略に直結する重要な論点だと考えています。
特に、以下の実務的な疑問をお持ちの方も多いのではないかと思われます。
- 既存のFIT認定事業がFIPに移行する際の契約上の留意点は?
- 出力制御順の変更は既存プロジェクトファイナンスにどう影響するのか?
- 非FIT/非FIP事業に対する規制強化の実務的インパクトは?
- セカンダリー市場での太陽光発電所取得時のデューデリジェンスで何を確認すべきか?
本記事では、これらの実務的論点を念頭に置きながら、最新の政策動向を深掘りしていきます。
再エネ主力電源化に向けた「自立化」の本質的意義
FIT/FIP制度の大前提:将来的な支援からの独立
FIT/FIP制度は、再エネのコスト競争力が他電源と比較してまだ十分ではない段階において、国民負担(賦課金)により価格支援を行うことで導入拡大を図り、スケールメリットや習熟効果を通じてコストダウンを実現するための時限的な制度です。
重要なのは、この制度の大前提が、将来的にFIT/FIP制度による支援がなくても新規の電源投資が進展する状況まで再エネが自立化することにあるという点です(資源エネルギー庁「資料1」p.2)。
この「自立化」という概念は、単なる建前ではなく、制度設計の根幹に関わる重要な要素です。
実際、FIT制度の導入当初から、将来的には市場競争力のある電源として自立することが前提とされていました。
電源種別ごとの自立化に向けた進捗と実務的課題
再エネの自立化に向けた進捗は、電源の特性や導入状況によって顕著な差異が見られます。以下の表は、政府資料に基づく整理に、実務的な論点を加えたものです。
| 電源区分 | 特性・目標 | 支援の方向性(実務的論点) | 実務的な留意点 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電・陸上風力 | コストダウンが進展。既に非FIT/非FIP案件も形成されつつあり、自立化の道筋の検討を加速化 | 大規模事業用太陽光などでは、2027年度以降の支援のあり方や価格水準について検討を加速 | コーポレートPPA等の相対契約が増加傾向。需要家との直接契約における価格交渉では、FIT/FIP価格が比較指標となるため、今後の価格設定動向を注視すべき |
| 中小水力・地熱 | 稼働期間が長い特徴を持つが、開発リスク/コストが高い | FIT/FIP制度終了後も長期安定稼働を確保しつつ、中長期的に緩やかなコストダウンを目指す | 地熱は開発期間が10年超に及ぶケースもあり、許認可リスクと地域住民との合意形成が最重要課題。資源量調査段階での支援継続が実務上不可欠 |
| 洋上風力 | 国内では黎明期。投資額が大きく、総事業期間が長いため、収入・費用の変動リスクが大きい | 今後の大規模化や産業基盤の構築を通じてコストダウンを目指す。中長期的見通しを明確にしながら支援のあり方を検討 | 公募占用指針における価格上限の設定が事業性判断に直結。サプライチェーンの国内構築が遅れており、外資依存リスクへの対応が課題 |
| バイオマス | 発電コストの大半を燃料費含む運転維持費が占め、自立化への課題が大きいコスト構造 | 燃料供給サプライチェーンの強化・構築を確認した上で、支援のあり方を検討 | 持続可能性基準の厳格化により、パーム油等の輸入燃料への依存に批判が集中。国産木質バイオマスの安定調達体制構築が鍵 |
実務上の重要ポイント
足元のインフレ環境下で建設費等の上昇が見られる電源も現れていますが、機械的に一律で想定値の引き上げを行うのではなく、「自立化に向けた取り組みがなされているか」や「事業が特に効率的に実施されている場合においてもコスト上昇が生じているか」を確認した上で、総合的に判断して価格への反映を行うべきだとされています(同p.2)。
これは実務的には、事業者が調達価格等算定委員会に対してコスト上昇の根拠を示す際、単なる市況データの提示だけでは不十分であり、自社の効率化努力や技術革新への投資実績を併せて説明する必要があることを意味します。
FIP制度の活用促進に向けた政策的加速化策
電力市場への統合の鍵となるFIP制度は、再エネ発電事業者の収入が電力市場価格(スポット市場価格等)と連動するため、事業者に需給に応じた電力供給を促す効果があります。
FIP制度の現状:まだ黎明期
2025年3月末時点でのFIP認定量は、新規認定・移行認定を合わせて約3,795MW(1,889件)となっており、FIT/FIP制度全体の認定量に占める割合は出力ベースでわずか約3.7%にとどまっています(資源エネルギー庁「資料1」p.24)。
将来的には全再エネ電源のFIP移行が望ましいことから、政府は以下の具体的な事業環境整備を実施していく方針を明確にしています。
ゲームチェンジャー:優先給電ルールにおける出力制御順の見直し
実務上、最も注目すべき政策変更が、優先給電ルールにおける出力制御順序の見直しです。
再エネ最大導入(kWhベース)を図るため、出力制御の公平性を確保しつつFIPへの移行を促す措置として、早ければ2026年度中から、優先給電ルールにおける出力制御の順番を、FIT電源→FIP電源の順とする方針が明確化されました(同p.27)。
実務的な影響分析
この措置が実行されると、FIP電源(太陽光・風力)は当面、出力制御の対象とならない一方、FIT電源の出力制御確率は増加することとなります。これは、FIT事業者にとって以下の実務的影響をもたらします。
- プロジェクトファイナンス契約への影響
多くのFIT案件では、金融機関との融資契約において想定売電収入をベースとした財務コベナンツ(財務制限条項)が設定されています。
出力制御の増加は想定売電量の前提を崩すため、コベナンツ違反リスクが生じる可能性があります。
事業者は金融機関との事前協議を行い、必要に応じて契約条件の見直し(ウェーバーの取得等)を検討すべきでしょう。 - FIP移行の経済的インセンティブ
出力制御による売電収入の減少リスクを回避するため、FIT事業者がFIPへの移行を検討する動機付けとなります。
ただし、FIP移行には発電計画の策定、バランシングコストの管理、市場価格変動リスクの負担など、新たな事業運営上の課題も伴うため、総合的な事業性評価が不可欠です。 - 既存PPA契約の見直し必要性
オフテイカー(電力購入者)との間でコーポレートPPA契約を締結している場合、出力制御の増加が契約上の供給義務に影響を及ぼす可能性があります。
契約書における不可抗力条項や出力制御時の取扱いを再確認し、必要に応じて覚書等で明確化することが望ましいと考えられます。
FIP移行を支える経済的インセンティブ:バランシングコスト増額措置
FIP制度では、発電計画の策定や予測対応に要する費用としてバランシングコストが交付されています。
今般の出力制御順の変更と併せて、再エネ電源が電力市場価格の低い時間帯から高い時間帯へ供給シフトを行うなど、高度な取り組みを円滑に実施できるよう、2025年度以降のバランシングコストの増額措置が講じられることとなりました(同p.36)。
具体的には、2025年度のバランシングコストの増額分は+1.00円/kWhと設定されています(同p.36)。
この増額措置は、出力制御順の変更によりFIT電源の買取量が減少することで生じる国民負担抑制効果の範囲内において限定的に活用されるため、結果としてFIT電源への支援をFIP電源への支援にリバランスする効果があると評価できます。
実務的示唆
バランシングコストの増額は、FIP事業者にとって予測精度向上や蓄電池併設への投資インセンティブとなります。
特に、気象予測サービスやアグリゲーターとの連携により、市場価格の高い時間帯に供給をシフトできれば、プレミアム収入とバランシングコストの双方を最大化できる可能性があります。
非化石証書の直接取引拡大とコーポレートPPAへの影響
FIP制度では、再エネ発電事業者が自ら非FIT証書(環境価値)を販売しますが、その取引環境も整備されています。
2021年度以前に営業運転を開始したFIT電源がFIPに移行した場合でも、2025年1月発電分から、発電事業者と需要家間の直接取引が認められました。
これは需要家のニーズの高まりを踏まえた措置であり、RE100参加企業やScope2削減を目指す需要家様にとっては、調達オプションが拡大する重要なポイントだと考えています。
実務的な確認事項
コーポレートPPAを検討される需要家の皆様は、以下の3点を確認されることをお勧めします。
- 既存PPA契約に非FIT証書の取扱規定が含まれているか
契約書において、環境価値(非化石証書、J-クレジット等)の帰属や費用負担が明確に規定されているかを確認すべきです。
特に旧来の契約では、FIT電源を前提としており環境価値の取扱いが曖昧なケースも見受けられます。 - FIP移行後の証書価格変動リスクをどう分担するか
非FIT証書は市場で取引されるため、価格が変動します。
長期契約においては、固定価格とするか、市場連動とするか、あるいは上下限を設けるか等、価格メカニズムを明確に合意しておくことが紛争予防の観点から重要です。 - 2030年までのFIP電源調達計画を策定しているか
後述するJPEAのロードマップでは、2030年までにFIP比率25%超を目指しています。
需要家としても、中長期的な再エネ調達戦略の中でFIP電源からの調達をどう位置づけるか、計画的に検討する時期に来ていると考えられます。
FIP併設蓄電池への規制緩和:系統側充電の解禁
また、FIP電源に併設する蓄電池について、先行案件に加え、2025年4月より、2023年度以前に新規認定を受けたFIP電源(FITから移行した電源を含む)についても、系統側からの充電が認められるようになりました。
これは蓄電池の稼働率を向上させ、需給バランス確保への貢献を効率化する措置であると考えられます。
実務的には、系統側から充電した電力を市場価格の高い時間帯に放電することで、収益機会を拡大できる可能性があります。
業界団体の本気度:太陽光発電協会のFIP移行ロードマップ
業界団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)は、太陽光発電のFIP移行を加速させるためのロードマップとアクションプランを策定しています。
野心的な数値目標:2030年FIP比率25%超
JPEAは、2024年3月末時点で0.8%であった太陽光発電のFIP比率(容量ベース)を、2030年までに25%超(約23GW)に高めることを目標として掲げています(太陽光発電協会「資料2」p.2)。
この目標達成には、発電事業者、需要家、および金融機関による行動変容が不可欠であるとJPEAは認識しています。
ステークホルダー別の期待される行動変容
発電事業者:
- FIP制度への積極的移行
- 蓄電池併設や発電予測精度の向上
- アグリゲーターとの連携強化
需要家(オフテイカー):
- 再エネ電源調達の拡大(現状1GW程度から23GWを超えるニーズへ)
- 長期PPA契約の締結による事業の予見可能性向上
金融機関:
- FIP活用電源への融資枠の拡大
- 市場価格変動リスクを織り込んだファイナンス手法の開発
実務的示唆:
この業界全体でのFIP市場の活性化への取り組みは、単なる業界団体の方針表明にとどまらず、政府の政策目標と連動した産業構造の転換を意味するものと考えられます。
国際比較:日本のFIP制度とASEAN諸国の再エネ支援策
私が実務で関わることの多いASEAN地域では、各国が再エネ導入支援策として様々なアプローチを採用しています。日本のFIP制度をASEAN主要国と比較すると、以下のような特徴が見えてきます。
| 国 | 主要な支援制度 | 市場統合の進展度 | 日本との比較 |
|---|---|---|---|
| ベトナム | Direct PPA + 固定価格買取(FIT的) | 低 | 政府がPPA価格を規制。市場メカニズムの導入は限定的 |
| タイ | 競争入札制度(EGAT主導)+民間PPA | 中 | 政府主導の入札が中心だが、民間PPAも拡大傾向。日本のFIPのような市場連動型は未導入 |
| インドネシア | FIT中心、一部競争入札 | 低 | PLNとの長期FIT契約が主流。FIP類似制度は未導入 |
| フィリピン | 再生可能エネルギー証書制度(REC)+卸電力市場 | 中高 | 卸電力市場が機能しており、市場統合の素地あり。ただし制度的複雑性が課題 |
| 日本 | FIP制度+非化石証書市場 | 中高 | 出力制御ルールの透明性、非化石証書の直接取引など制度設計の先進性が特徴 |
実務的示唆:
日本のFIP制度は、出力制御ルールの透明性や非化石証書の直接取引など、制度設計の先進性において、ASEAN諸国が今後市場統合型の再エネ支援策を導入する際のモデルケースとなる可能性があると考えられます。
特に、ASEAN地域で再エネ事業を展開する日本企業にとって、日本国内でのFIP制度運用ノウハウは、現地での政策提言や事業スキーム構築において競争優位性となり得るでしょう。
地域共生と事業規律の強化:社会的信頼性の確保
再エネを最大限導入するためには、地域との共生と国民負担の抑制を図ることが大前提であり、特に太陽光発電においては、一部で自然環境や景観への配慮に欠けた事案が見られることから、地域との共生に向けた事業規律の強化が喫緊の課題となっています。
行政による全省庁横断的な監視体制の構築
行政側では、太陽光発電事業における公益(生活環境、自然環境、景観の保全、安全性確保など)との調整を図るため、関係省庁連携の下で各法令の総点検が行われています。
事業規律の強化の一環として、「全省庁横断再エネ事業監視体制」が構築されており、資源エネルギー庁は現地調査を行う「再エネGメン」を運用しています。
実務上、特に注目すべき点は、これまでFIT/FIP認定事業が対象であった「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」について、非FIT/非FIP事業も通報対象に追加することで、国内の全ての太陽光発電事業に対する規律強化を図る方針であることです(資源エネルギー庁「資料3」p.3, 6)。
運用実績:
2025年10月時点で、926自治体(47都道府県+879基礎自治体)がこのシステムを利用し、116件の通報を受けています(同p.6)。違反が確認された場合は、事業者に対する指導や、FIT/FIP交付金一時停止などの行政処分が厳格に実施されています。
実務的な対応策:
全ての太陽光発電事業者(非FIT/非FIP事業を含む)は、以下の対応を早急に実施すべきでしょう。
- コンプライアンス体制の総点検
森林法、宅地造成等規制法、景観法、種の保存法、文化財保護法など、関係法令の遵守状況を改めて確認する。 - 自治体との事前協議の徹底
許認可が不要な規模の案件であっても、自治体への事前説明や任意の協議を積極的に実施し、地域の理解を得る努力を怠らない。 - 内部通報制度の整備
社内で法令違反の兆候を早期に発見し是正できる体制を構築する。
業界による自主的な行動規範:JPEAの取組方針
JPEA自身も、「地域との共生・共創」及び「自然環境配慮と生物多様性の保全」を行動規範とし、「事業者による責任ある行動と望ましい取組」を宣言しています(太陽光発電協会「資料4-1」p.1-2)。
行動規範の主要項目(実務的ポイント):
- 計画段階からの地域対話
説明会の実施等(非FIT/非FIP設備も対応に努める)、地域住民の声を尊重し、地域と共に事業を推進する姿勢で臨む。 - 安全・安心の確保
災害発生リスク、自然環境や景観(反射光含む)に十分配慮した立地場所選定と開発計画。 - 環境影響評価の実施
法令に基づくもしくは自主的な環境影響評価を行い、専門家や自治体とも連携して影響低減に最大限配慮。用地範囲の変更も含めた柔軟な対応。 - 適切な維持管理と長期安定稼働
地域に配慮した事業運営と適切な維持管理により長期安定稼働を実現。 - 地域経済への貢献
地域雇用や経済への積極的貢献。
セカンダリー取引における実務的配慮:買手のデューデリジェンス
実務上、極めて重要な論点として、事業の売却・譲渡(セカンダリー取引)に関する配慮があります。
JPEAは、発電事業者がセカンダリー市場で取引を行う際には、事業のリスク評価(「太陽光発電事業の評価ガイド」全162項目の活用)を行い、設備が適切に維持・管理されているか確認することを推奨しています(同p.3, 7, 9)。
実務的な重要性:
これは、地域とのトラブルを抱えた問題案件が市場で流通することを防ぎ、地域に配慮した事業者の参入を促すための極めて重要な取り組みです。
買手側のデューデリジェンスで確認すべき事項:
- 地域住民との合意事項の有無と内容
売主から、地域説明会の議事録、住民との覚書、苦情対応履歴等の提供を受け、継承すべき義務を明確化する。 - 関係法令の遵守状況
許認可の取得状況、条件遵守状況、行政指導歴の有無等を確認。特に森林法の林地開発許可条件や宅地造成等規制法の造成許可条件の遵守は重点的にチェック。 - 評価ガイド162項目に基づく技術的評価
土地・権原、土木・構造、発電設備の3分野について専門家による詳細評価を実施。 - 将来の廃棄・リサイクル費用の積立状況
廃棄費用の外部積立状況を確認し、将来の事業終了時の負担を見積もる。
次世代技術への期待:ペロブスカイト太陽電池(PSC)の戦略的位置づけ
主力電源化の達成と地域共生の両立に貢献する次世代技術として、ペロブスカイト太陽電池(PSC: Perovskite Solar Cell)が政策的に強く期待されています。
PSCの技術的特徴と導入の意義
PSCは、軽量・柔軟という特徴を活かし、これまで太陽電池の設置が困難であった建物の屋根、壁、窓など、需要地に近接した設置が可能となります。
日本は国土面積当たりの太陽光導入容量が既に主要国の中で最大級の水準に達しており、平地への大規模太陽光発電所の新規開発余地は限定的です。
こうした中で、需要地近接型のPSCの活用は、地域共生と導入拡大を両立するための鍵となるでしょう。
政府目標:2040年に向けた野心的ターゲット
「次世代型太陽電池戦略」に基づき、PSCについては以下の野心的な目標が設定されています(資源エネルギー庁「資料1」p.15, 19)。
- 2040年までの累積導入量:約20GW
- 2040年までの発電コスト:10〜14円/kWh以下
また、PSCの主要な原材料であるヨウ素について、日本は世界第2位の産出量(シェア約30%)を誇ります。国産資源を活用した強靭なサプライチェーン(供給網)の構築を通じて、エネルギーの安定供給にも資することが期待されます。
実務的な視点:短期的事業判断には慎重な見極めが必要
ただし、実務的な観点からは、PSCは2040年に向けた長期戦略であり、短期的な事業判断には慎重な見極めが必要であることを強調しておきたいと思います。
現時点での課題:
- 商用化のタイムライン不確実性
耐久性(寿命)の向上、製造プロセスの確立など、商用化に向けた技術的課題が残存。 - 規制・認証制度の未整備
建築物への設置を想定した場合、建築基準法上の取扱い、防火性能等の基準が今後整備される必要がある。 - 初期コストの不透明性
量産効果が発揮される前の初期段階では、コストが想定より高止まりするリスク。
事業者へのアドバイス:
PSC関連の技術開発動向や実証プロジェクトの成果を注視しつつ、実際の事業投資判断は商用化の確度が高まってから行うことが賢明でしょう。一方、研究開発段階での参画や実証事業への協力は、将来の競争優位性確保の観点から検討に値すると考えられます。
まとめ
今回は、2025年11月12日開催の総合資源エネルギー調査会・再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第77回)の配布資料を基に、日本の再エネ主力電源化戦略の最新動向を、弁護士としての実務的視点から解説してきました。
実務上の重要ポイント(再確認)
FIP移行加速化:2026年度からの出力制御順変更がもたらす実務的影響
早ければ2026年度からFIT電源よりFIP電源の出力制御順が優先されることは、既存FIT事業者にとって事業計画見直しの重要な契機となります。
今すぐ検討すべきこと:
- プロジェクトファイナンス契約における財務コベナンツへの影響分析
- 金融機関との事前協議とウェーバー取得の要否検討
- FIP移行の事業性評価(バランシングコスト、市場価格変動リスク等の総合判断)
- オフテイカーとのPPA契約における出力制御時の取扱い明確化
地域共生の強化:非FIT事業も規制対象、全事業者にコンプライアンス強化が必須
非FIT/非FIP事業も「再エネGメン」の監視対象となり、全ての太陽光発電事業者にコンプライアンス体制の抜本的強化が求められています。
今すぐ実施すべきこと:
- 関係法令(森林法、景観法、種の保存法等)の遵守状況の総点検
- 自治体への事前協議・説明の徹底(許認可不要案件も含む)
- セカンダリー取引時のデューデリジェンスにおける評価ガイド162項目の活用
次世代技術PSC:2040年目標は長期戦略、短期的事業判断は慎重に
ペロブスカイト太陽電池は2040年に累積20GW、発電コスト10〜14円/kWh以下を目指す政府の長期戦略です。技術的ポテンシャルは高いものの、商用化までの不確実性を考慮し、短期的な事業投資判断は慎重な見極めが必要です。
推奨アプローチ:
- 技術開発動向や実証プロジェクトの成果を継続的にモニタリング
- 実証事業への参画による将来的な競争優位性の確保を検討
- 実際の大規模投資判断は商用化の確度が高まってから実施
今後の注目ポイント
本小委員会の議論から、以下の論点が今後の実務上の注目ポイントになると考えられます。
- 2026年度のFIP移行実績
JPEAが掲げる2030年FIP比率25%超の目標に対し、2026年度の実績がどの程度進捗するかが、政策の実効性を測る重要な指標となります。 - 全省庁横断監視体制の運用実態
非FIT/非FIP事業への監視拡大後、実際の通報件数や行政処分の内容がどう推移するかを注視する必要があります。 - PSC商用化のタイムライン
実証から商用化への移行時期が明確になることで、事業者の投資判断も具体化していくでしょう。 - 2027年度以降のFIT/FIP価格水準
大規模事業用太陽光などの自立化に向けた検討が加速される中、2027年度以降の調達価格がどう設定されるかは、新規投資判断に直結します。
再エネ事業に携わる皆様、そしてESG経営を推進される企業様におかれましては、これらの政策動向を注視しつつ、実務的な対応策の検討を早期に進められることをお勧めします。
特に、FIP移行に伴う契約見直しや、地域共生を前提としたコンプライアンス体制の強化は、待ったなしの課題であると考えられます。
弁護士として、皆様の再エネ事業の成功と、日本の持続可能な社会の実現に、微力ながら貢献できれば幸いです。ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。






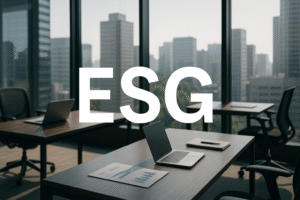


コメント